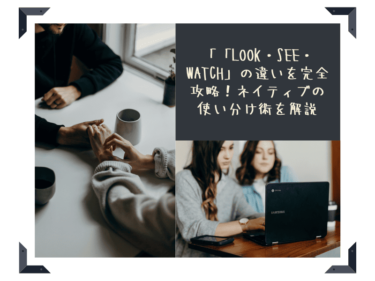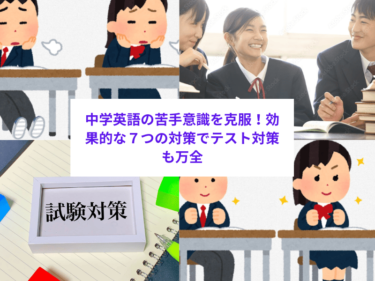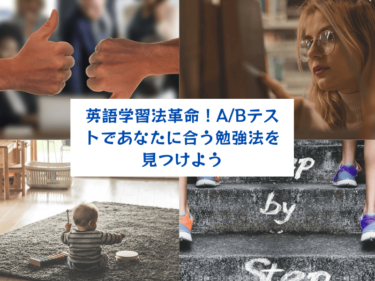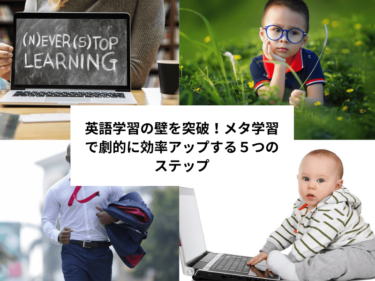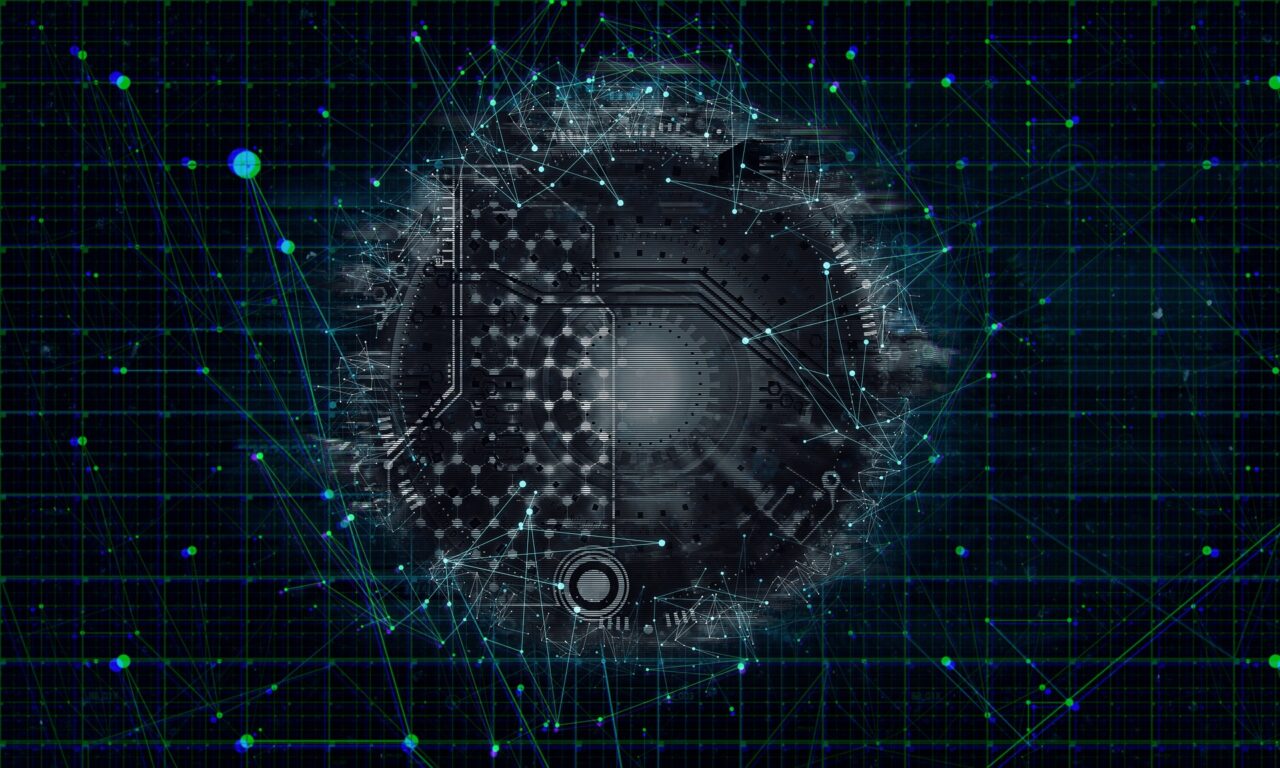「英語学習に行き詰まりを感じている」
「英語をもっと効率的に学びたい」
「試験や会話で使える実践的な英語力を身につけたい」
そんな悩みを抱えたことはありませんか?
従来の暗記中心の英語学習法では、これらの課題を十分に解決できないこともあります。
そこで注目されているのが 「マルチモーダル学習」 です。
視覚・聴覚・触覚といった複数の感覚を活用し、英語学習の成果を最大化するこの方法は、近年多くの研究や実践でその効果が実証されています。
この記事では、マルチモーダル学習の基本的な考え方から、具体的な成功事例、そしてすぐに実践できる学習ステップまでを解説します。信頼できるデータや専門家の見解を交えながら、あなたの英語学習を次のレベルへ引き上げるヒントをご提供します。
マルチモーダル英語学習とは?

マルチモーダル英語学習を知っとく前に、マルチモーダル学習の基本概念を知ることが重要です。
マルチモーダル学習とは、複数の感覚(モード)を活用して学ぶ方法を指します。
「マルチモーダル(Multimodal)」とは、「多様なモードを持つ」という意味で、視覚、聴覚、触覚、発話、身体の動きなどを統合的に利用する学習法です。
英語学習においては、例えば以下のような方法がマルチモーダル学習に該当します。
- 音声を聞きながら、関連する画像や動画を見る
- 英語のフレーズを聞いた後、自分で発音し、文字として書き留める
- 実際の場面を模したシミュレーションやロールプレイを行う
これにより、脳内での情報処理が多層的になり、記憶の定着や実践力の向上が期待できます。従来の「読む」「聞く」だけに依存した学習法とは異なり、複数の感覚を総動員することで、より自然に英語が身につくと言われています♪
従来の学習法との違い
従来の英語学習法は、多くの場合、以下のような特徴がありました。
一方向的な学習
教材を読む、リスニングをする、といった単一モードでの学習が中心でした。
暗記重視
文法や単語を「覚える」ことに重点が置かれ、使う機会が少ない学習方法が一般的でした。
実践の欠如
会話や実際の場面で使うシミュレーションが不足しており、知識はあっても「話せない」という悩みを持つ学習者が多くいました。
以上に対し、マルチモーダル学習は以下の点で優れています。
双方向的で実践的
実際に話したり書いたりするなど、能動的な学習が可能です。
複数感覚を活用
音声、視覚、動作を同時に取り入れることで、記憶の定着率が高まるとされてます。
実用的なスキルの習得
実際の生活や仕事で役立つスキルを自然と身につけられるため、学習内容が即座に応用可能です。
なぜ今マルチモーダル学習が注目されているのか

マルチモーダル学習が注目される背景には、教育学や認知科学の進歩、そして技術革新があります。
教育学と脳科学の発展
近年の研究では、人間の脳が複数の感覚を統合的に処理することで学習効果が向上することが明らかになっています。視覚と聴覚を同時に使うことで記憶の保持率が大幅に高まることや、実際に体を動かすことで脳がより深く情報を処理することが確認されています。
テクノロジーの進化
デジタルデバイスやAIの普及により、音声認識技術、VR/AR(仮想現実・拡張現実)を活用した学習が可能になりました。これらの技術は、マルチモーダル学習をさらに身近で実践的なものにしています。
例:音声アシスタントを使った発話練習、字幕付き動画でのリスニング強化、VRを用いた海外旅行シミュレーションなど
英語を使う場面の増加
グローバル化が進む中で、英語は単なる試験科目ではなく、実際に使えるスキルとして求められています。リスニングやスピーキング、リーディングといったスキルをバランスよく学ぶ必要性が高まっており、これを効率よく実現できる方法としてマルチモーダル学習が注目されています。
マルチモーダル学習の効果を支える科学的根拠

人間の脳は複数の感覚を統合的に処理する能力を持っていることは前述した通り。
これを「マルチモーダル処理」と呼びます。視覚や聴覚、触覚といった異なる感覚情報は、大脳皮質のさまざまな領域で連携して処理されることで、より深い理解と記憶の定着が可能になります。
例えば、次のようなことが脳科学の研究で明らかになっています。
視覚と聴覚の統合
聴覚情報(音声)を聞きながら視覚情報(映像や文字)を同時に受け取ると、脳の記憶を司る海馬が活性化され、単一のモードで学習する場合よりも記憶の定着率が向上します。
身体の動きと記憶の関係
実際に手を動かして書いたり、体を使って動作を伴う学習を行うと、脳の運動皮質や感覚皮質が刺激され、記憶がより強固なものとなります。このプロセスは「体性感覚統合」とも呼ばれています。
複数の感覚を活用することで得られる学習効果
マルチモーダル学習による具体的な効果として、以下の点が挙げられます。
①記憶の保持率が向上する
視覚と聴覚を組み合わせることで、情報を異なる経路から同時に記憶するため、単一の感覚だけで学ぶよりも長期間記憶が保持されやすくなります。例えば、リスニングだけではなく、スクリプトを一緒に読むことで内容の理解が深まるという結果が多くの学習者で報告されています。
②学習効率が高まる
複数の感覚を使うことで脳が情報をより効率的に処理するため、短時間でも学習効果が得られやすくなります。例えば、英語の映像を見ながら関連する単語やフレーズを発音する学習は、リスニング、リーディング、スピーキングのスキルを同時に強化が可能です。
➂応用力が身につく
実際の場面で使う英語は、単一のスキル(例:リスニングやリーディング)のみでは対応が難しいことがあります。マルチモーダル学習を通じて、状況に応じた柔軟な応用力が鍛えられます。例えば、旅行先での会話シミュレーションでは、発音やリスニングに加え、状況に応じた表現力が磨かれます。
国内外の研究結果と具体例
マルチモーダル学習の効果を裏付ける研究は数多く存在します。その中から特に注目すべき成果をいくつか挙げます。
米国カーネギーメロン大学の研究(2016年)
内容:視覚(動画)と聴覚(音声)を組み合わせた英語学習を行ったグループと、音声のみで学習したグループを比較。
結果:視覚・聴覚を同時に活用したグループのほうが、学習内容の定着率が約30%向上した。
日本の小学校における実践例(文部科学省研究)
内容:デジタル教材を活用して英語を学ぶ授業を実施。特に、映像、音声、アニメーションを組み合わせた教材を導入。
結果:映像と音声を組み合わせた学習により、児童の単語理解と発音精度が向上したほか、学習への興味や集中力も高まった。
VRを活用した英語学習(欧州連合のプロジェクト)
内容:VR環境で日常会話や旅行先でのシチュエーションを再現し、学習者が体験的に英語を学ぶ手法を導入。
結果:学習者は、現実の場面でも緊張せずに英語を使えるようになり、スピーキングスキルが大幅に向上した。
成功事例:マルチモーダル学習で英語力が向上した人たち

マルチモーダル学習で英語力向上に成功した事例を紹介します。
ビジネス英語を短期間で習得した社会人の体験談
背景
貿易関連会社に勤めるHさんは、海外取引先とのやり取りで英語が必要となり、3か月以内にビジネス英語を習得する必要がありました。しかし、忙しい仕事の合間を縫っての学習に不安を感じていました。
マルチモーダル学習の実践
Hさんは、効率を重視した以下の方法を採用。
パワーポイントの資料を作成し、スライドの内容を英語で説明する練習を行い、録音して自己チェック。
テンプレートを参考に、実際の取引で使うメール文を作成し、音声読み上げ機能を使って読み上げ確認。
海外のパートナー企業を想定し、上司や同僚と模擬会議を行い、リアルな場面での発言練習を反復。 |
結果
3か月後には英語でのプレゼンやメール作成がスムーズにできるようになり、初めて参加した国際会議でも自信を持って意見を述べられるようになりました。特に、リアルなシミュレーションを繰り返すことで、実践力が身についたと話しています。
英会話が苦手だった学生の成功ストーリー
背景
高校生のDさんは、文法や単語の暗記は得意でしたが、英会話となると緊張して言葉が出てこないのが悩みでした。学校の授業や模試では一定の成績を維持していたものの、スピーキングテストや面接対策になると苦戦していました。
マルチモーダル学習の実践
Dさんは、視覚、聴覚、発話を組み合わせた以下の方法を実践。
映像付きの英語教材を使用し、音声を聞きながら字幕を目で追い、重要なフレーズを発音。
映像に出てくる話者のジェスチャーを真似しながら、セリフをリピートする練習を毎日10分実施。
仮想の外国人講師と英語での会話練習を体験。自宅で緊張せずにスピーキングの練習ができました。 |
結果
1か月後には、自信を持ってスピーキングテストに臨めるようになり、以前より流暢に話せるようになりました。また、ジェスチャーを交えることで自然な会話ができるようになり、英語のコミュニケーションが楽しく感じられるようになったとのことです。
子どもの英語教育における成果と保護者の声
背景
小学生のT君は英語の授業が始まったばかりで、まだアルファベットや簡単な単語しか知らない状態でした。しかし、親が早期の英語教育に関心を持ち、自宅でも積極的に学習させたいと考えていました。
マルチモーダル学習の実践
T君の家庭では、子ども向けに工夫した以下の方法を導入。
有名な英語の童謡を流し、一緒に歌いながら踊ることで楽しく発音やリズムを学習。
絵本を親が読み聞かせ、アプリでキャラクターの声を聞きながら単語を反復練習。
スマホやタブレットを使い、英語の単語に関連する3Dアニメーションを表示しながら遊び感覚で学習。 |
結果
1年後には、T君は簡単な英語のフレーズで家族と会話を楽しむようになり、学校の授業でも積極的に発言するようになりました。保護者からは「遊びながら学べる教材を使ったことで、子どもの興味と集中力が持続した」と高く評価されています。
実践ステップ:マルチモーダル英語学習を始める方法 の導入文を作成して

マルチモーダル学習を始めるために必要な教材とツールの選び方、効果的な学習環境の整え方、そして毎日取り組める具体的なアクティビティをご紹介します。
必要な教材とツールの選び方
マルチモーダル学習を成功させるためには、目的に合った教材とツールを選ぶことが重要です。以下は具体的な選び方のポイントです。
教材の選び方
| 初心者向け
絵本や簡単なストーリー付きの教材(例:オックスフォードリーディングツリー ) 英語の歌やリズム感を鍛える教材(例:Super Simple Songs ) 中級者以上 映画やドラマを題材とした教材(例:TED Talks 、BBC Learning English ) 専門分野の語彙や表現を含む書籍や記事(例:ビジネス英語 や TOEIC用教材 ) 子ども向け |
ツールの選び方
| 視覚と聴覚を活用
動画配信サービス(例:YouTube、Netflix) 音声認識機能付きのアプリ(例:Duolingo 、Speak ) 触覚や体験を重視 VR/AR対応アプリ(例:Mondly VR ) 英語のスピーキングを録音できるツール(例:ボイスメモアプリ) 組み合わせた学習を支援 |
効果的な学習環境の作り方
学習環境を整えることで、モチベーションが向上し、習慣化しやすくなります。以下のポイントを参考にしてみてください。
家庭での学習環境
| 静かな場所を確保
集中しやすい部屋やコーナーを用意し、ノイズを最小限に抑える工夫を。 学習専用スペースを作る 教材やツールを一か所にまとめておく。 ホワイトボードやノートを使って進捗を記録するスペースを設ける。 デジタルデバイスの活用 スマホやタブレットを学習専用に設定。通知をオフにして学習に集中できる環境を整える。 |
外部環境
| 英語を使える機会を増やす
英会話カフェやオンライン英会話に参加。 国際交流イベントや旅行先で英語を使う体験を積む。 現地の雰囲気を再現 海外の風景や街並みを映した動画を流す。 好きな海外の飲み物やスナックを用意して臨場感を高める。 |
毎日取り組むべき具体的なアクティビティ
継続的な学習には、日々のルーティンに組み込めるアクティビティが鍵です。
中級者以上向け
| シャドーイング
映画やニュースを聞きながら、スピーカーの発音やイントネーションを模倣する。 日記を英語で書く 短文でも良いので、毎日の出来事や感想を英語で記録する習慣をつける。 英語で考える練習 日常生活で見たものや考えたことを頭の中で英語に変換してみる。 |
初心者向け
| デイリーフレーズの学習
毎日3~5つの簡単なフレーズを学び、繰り返し発音や書き取りを行う。 リスニング+模倣 子ども向けの歌や短い会話を聞きながら、繰り返し真似する。 単語カードを使った練習 イラストや写真付きの単語カードで視覚的に語彙を増やす。 |
子ども向け
| インタラクティブゲーム
英語を使って答えるクイズや単語探しゲームで楽しみながら学ぶ。 親子での英語会話 家庭内で簡単な英語を使った会話を試してみる。例:「What do you want to eat?」 絵本の読み聞かせ+発音練習 親子で英語の絵本を読んで、キャラクターの声を真似しながら学習。 |
マルチモーダル学習を最大限に活用するコツ

学習においては「時間管理」、「モチベーション維持」、そして「学習進捗の可視化」がとても重要なので、そのコツを紹介します。
効率的に成果を出す時間管理法
学習の質を高めるには、計画的な時間管理が不可欠です。以下の方法で効率を最大化しましょう。
学習時間を小分けにする
| ポモドーロ・テクニックを活用
25分集中+5分休憩を1サイクルとして、疲れずに学習を進める。朝、昼、夜に短時間の学習を分散させると、習慣化しやすくなります。 目的別に時間を割り当てる リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングをバランスよく学習するため、1日の中でそれぞれの時間を確保。例:朝はリスニング、昼はライティング、夜はスピーキング練習。長期目標(例:TOEICの点数向上)などを達成するために、週単位でのスケジュールを立てる。 スキマ時間を活用する 通勤中や移動時間にはリスニング教材を使う。待ち時間には単語カードや英語アプリで語彙を増やす。 |
モチベーションを維持するための工夫
楽しさと達成感を感じられる仕組みを作ることがモチベーション維持の鍵です。
短期目標を設定する
| 1週間で覚える単語数や話せるフレーズ数を決め、小さな成功体験を積み重ねる。そして、ゴール達成時には、自分へのご褒美を用意する(例:好きな映画を見る、カフェでリラックスするなど)。
多様な教材で飽きさせない 好きなテーマに関連した教材(例:好きな映画の英語字幕版、好きなジャンルのポッドキャスト)を使い、学習をエンターテイメント化する。また、ゲーム感覚で学べるアプリ(例:Duolingo、Kahoot!)などを取り入れる。 学習仲間を見つける 英会話カフェやオンラインの学習コミュニティに参加して、切磋琢磨できる仲間を作る。そして、SNSで進捗をシェアし、他の学習者からフィードバックをもらう。 |
学習の進捗を可視化する方法
自分の成長を「見える化」することで、達成感と次へのモチベーションを高めることができます。
学習記録をつける
| デジタルツールの活用
学習管理アプリ(例:Notion、Trello)でタスクや進捗を記録。スマホの学習時間記録アプリ(例:Forest、Toggl)で集中時間を把握。 手書きノートの活用 習得した単語、フレーズ、達成したタスクをノートに記録し、振り返りに使う。 目標達成をビジュアル化 カレンダーに「学習済み」スタンプやシールを貼る習慣を作る。月単位で達成した項目をグラフ化し、進捗を視覚的に確認する。 定期的に自己テストを実施 学習開始時と現在のスピーキングやリスニング能力を録音して比較。公式の模擬試験やオンラインの無料テストでスコアの変化を確認。 |
未来の英語学習:マルチモーダルが切り開く可能性

マルチモーダル学習の新たな展開として、AIやVR(仮想現実)技術の融合による活用が注目されています。これらの技術は、学習者にリアルな体験を提供し、効果的な学習を支える重要な役割を果たしていくでしょう。
AI技術の進化
| 個別最適化された学習
AIが学習者の進捗や弱点を分析し、パーソナライズされた教材や課題を提案します。例えば、英語アプリ「ChatGPT」や「Grammarly」では、リアルタイムでフィードバックを提供し、自然な会話練習や文法の改善をサポートします。 自然言語処理(NLP)の応用 AIが文脈を理解し、学習者の発言に対してより適切な応答を返すことが可能に。これにより、スピーキングやライティング能力が飛躍的に向上します。 |
VR技術の応用
| 没入型の英語学習環境
VRを活用すると、英語圏の街並みや会話シチュエーションをリアルに体験可能。観光地での買い物や職場でのプレゼンテーションなど、実生活に近いシミュレーションができます。 臨場感のある学習 マルチモーダル要素(視覚、聴覚、触覚)を組み合わせることで、記憶の定着率が向上。VRゴーグルを使用した「英語での仮想旅行」は、学習を楽しい体験へと変えます。 |
これからの英語教育のトレンド
未来の英語教育を切り開く以下のトレンドに注目し、参考にしてみてください。
| トレンド1:ハイブリッド教育の拡大
オンラインと対面授業を組み合わせたハイブリッド形式が主流化。マルチモーダル学習は、この形式で効果を発揮し、リアルタイムのやり取りとデジタルツールの利点を両立します。 クラスルームでは、動画、インタラクティブゲーム、AR教材など多様な媒体を組み合わせて学ぶスタイルが増加しています。 トレンド2:マイクロラーニングの普及 短時間で特定のスキルを習得する「マイクロラーニング」の需要が高まっています。5~10分のスピーキング練習やリスニングクイズなど、スキマ時間に活用できる教材が豊富になっています。 トレンド3:インクルーシブな教育 個人の背景やニーズに応じた学習が重視されるように。例えば、聴覚障害者向けの字幕付き教材や、非ネイティブ向けの簡略化された教材が普及しつつあります。 |
マルチモーダル学習が世界に与えるインパクト
マルチモーダル学習は、個々の学習効果を高めるだけでなく、社会や文化に大きな影響を与えています。
| インパクト1:グローバル化の促進
言語の壁を越えたコミュニケーションが可能に。世界中の人々が、異なる文化をより深く理解し、交流を深めるきっかけとなります。 英語を学ぶことで、国際ビジネスや観光業がさらに活性化し、世界経済にも好影響を与えます。 インパクト2:教育の普及 テクノロジーを利用したマルチモーダル学習は、リソースの限られた地域でも英語教育を提供可能に。オンライン教材やアプリは、地理的な制約を解消します。 非英語圏の学生がより平等に教育を受けられる環境を実現し、学びの機会を広げます。 インパクト3:多文化共生社会の形成 英語学習を通じて、異文化理解が深まることで、多文化共生社会の実現が進みます。例えば、英語でのディスカッションや異文化交流イベントの増加が期待されます。 |
まとめ
マルチモーダル英語学習は、ただ英語を学ぶだけでなく、楽しみながら効果を実感できる方法です。小さな一歩から始めて、コツコツと続けていきましょう。未来の自分が、その努力に感謝する日が必ずやってきます。